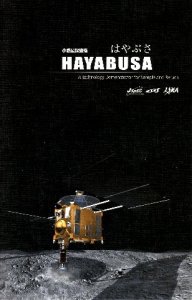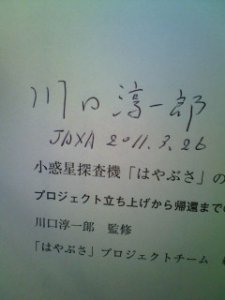- 2011/03/26 23:53
「はやぶさ」 人類初の往復の惑星飛行、その経緯
JAXA はやぶさプロジェクトマネージャー
川口 淳一郎 教授
始まりは東北関東大震災のお見舞いのメッセージから。
SPring-8主催の講演会とあってサンプルの分析関係の題材からスタート
子供向けに作られた資料だったようでひらがなが多かったです。
新しい内容も加わったり視点を変えた部分もあり面白かったです。
ちなみに今回の会場の平均年齢は50歳らしいです。
もっと若い人たちにも聴きに来て欲しいとおっしゃってました。
以前と同じ内容の部分は割愛します。
キュレーション作業の写真
・分析前の準備作業。何で出来ているかくらいは分析できる
サンプルキャッチャー
・直径8cm、高さは10cmちょい A室とB室に分かれている。
サンプルキャッチャーA室の状況(2回目)
・ピックアップは静電マニュピレーターで行った。
・カンラン石、斜長石、硫化鉄を含む岩石質のものが見つかった
・つまみ上げるのは効率が悪いのでへらでさっと掻き取ったら3000個の微粒子がみつかった。
そのうち半分は人工物 人工物はアルミの微粒子
・識別しやすいようにキャッチャー内部をアルミでコーティングしてあった。
・微粒子の大きさはスギ花粉とか黄砂ぐらい
SPring-8で1/22より分析が始まった
・大阪大学の土’山明先生がX線CTでサンプルの粒子の3次元形状および3次元内部構造を調べた。
・土’山先生は変人だった(情熱にあふれた人)
・アメリカで初期分析の発表があり盛況だった
イトカワのサンプルにより何がわかるか
・イトカワはどうやって作られたのか
・どうやら原始太陽系円盤→小天体→衝突により分裂→再び集合→イトカワ形成 らしい。
・イトカワの表面と隕石の表面は色(スペクトル)が違う
イトカワの表面はプロトンに晒されていて太陽風化を受けている証拠
地球はどうやってできたのか
・実は石がいつどこでどうやって出来たのかはよくわかっていない。= 太陽系が出来た謎
小惑星で何がわかるか
・地球のでき方を知る
・地震や気象の手がかりをつかむ
・地球は液体というより流動体なので丸くなる。重いものは沈み層になる。
一番上の地殻は軽い。石英(酸化ケイ素)が主成分
マントルは何で出来ているか? さらにその下は? 推測しかできない。
溶岩は一番軽いものが噴出しているだけで地球の中身がわかるわけではない。
地震などを調べるには地球の中身を知りたい。
↓
答えは小惑星にある。溶けていない天体の表面には重いものも軽いものもある
・小惑星は太陽系の昔を伝える化石である。
・さらに遠くへ行くと有機物、アミノ酸、水のふるさとがある→C型小惑星
・気候の変動の原因のCO2→C型小惑星でてがかりが
・生命の進化をはぐくんだ環境や気候の変化を知る
・はやぶさ2(仮称)ははやぶさで実証した技術を使って、全く異なる見たこともない天体(C型小惑星)へ向かう
月・惑星探査は最先端技術の結晶
・イオンエンジン→スパッタ成膜技術(マグネトロンスパッタ) タッチパネルやプラズマディスプレイ
・カーボン・カーボン→ジェットエンジンやタービンに使うと性能アップ
・ロボット(自律)技術→特殊作業ロボット
・効率の良い太陽電池
・燃料電池
・GPS、気象、放送衛星のサービス
・データ圧縮の基礎
・ビット誤りを自動検出し修復する符号化
ソーラー電力セイル
・ハイブリッド推進 光の圧力とイオンエンジン 日本オリジナルの技術
・イカロスで実験
ハイブリッド推進で木星やトロヤ群小惑星へ
・トロヤ群小惑星は太陽系の冷凍庫、タンパク質やもしかしたらDNAも見つかるかもしれない。
・地球の生命がどこから来たのかがわかるかも。
はやぶさのめざしたもの
・一番難しいサンプルリターン
・サンプルを取ってくればほんのわずかでも大きくて新しい技術で分析できる
はやぶさのネーミングについて
・サンプルを取るためのタッチダウンが鳥のハヤブサの狩りのようだから
・漢字の「隼」はあますところなく「はやぶさ」を現わしている。
・内之浦へ行く時に西鹿児島行き寝台特急「はやぶさ」に乗って行ったから。
・寝台特急「はやぶさ」が2008.3月に廃止になったとき「はやぶさ」の運命を示されたようでショックだった。 と思ったら東北新幹線で「はやぶさ」がもどってきた。
・E5系「はやぶさ」の名の由来は鳥のハヤブサが時速300km/hで飛ぶから、だそう。
「彼星(かなた)より宙に還った碧き君 いまは地を駆け夢の快走(回想)」
はやぶさの目的
・天体への往復飛行 オリジナルの発想
・思い切ったブレークスルーをもたらすのは→天の邪鬼であるのかも
どうしてこんな発想・着想が出来たか
・宇宙研の先輩たちはみな変人だった
「みえるものはみな過去である」 故・長友教授
「これまで学んだのは練習問題」 塚本さん
「教科書には過去しか書いていない」 学生へ
ここから以降は以前京大で聴いた講演とほぼ一緒でした。
・はやぶさのはじまり
・はやぶさはロボット
・はやぶさの故障
・弾丸は発射されていなかった
・通信途絶
・はやぶさの救出 はやぶさに手伝って貰った
・はやぶさ、そうまでして君は、
・神頼み
・カプセルの帰還
目指したのは世界初、必然的に世界一になる。
未来へ投資
・イノベーションの発揮にハイリスクな投資は必要
加点法の評価
耳のないせんべいを作らないこと
・耳が出来ないように材料を少なめに入れるとちゃんとしたせんべいができない
・ここで言うせんべいは南部せんべいのこと。
技術と根性
・運を実力に変える活動が必要
・アイディアで変革を
最後に
はやぶさで培った意地と忍耐。震災からの復興を目指す方々へ何かしらでも励ましになれば、と思うものです。東北、日本がんばりましょう。
質疑応答
クロス運転について
川口:空だきになったイオンエンジンが保ってくれた。
はやぶさは男の子?女の子?
川口:飛んでいるときは男の子。でもカプセルはたまごとかアンビリカルケーブルとか考えると…
将来人間は太陽系外へ行けるか
川口:可能です。飛行時間が問題
医学とのセットが必要では。代謝を制御するとか
小惑星への往復は10年レベルだけど、次の100年では大きな変革があるのでは。
SPring-8での解析
川口:はやぶさのサンプルは取ってきたものの半分は手つかずで残しておく
火星への有人飛行はイオンエンジンor化学エンジン?
川口:大きな電力が得られるならイオンエンジン
大きな電力を得るにはやっぱり原子力になるだろう
イトカワへの不時着と故障
川口:1回目は予想外に成功だったと思っている。
想定していないにもかかわらず温度の比較的低いところに着陸し続けた
はやぶさは1年後にスウィングバイしたがもっと早くにはできないのか
川口:軌道変更は人為的には大きな変更は出来ない。惑星の公転エネルギーを使う
地球と同期するには最短でも半年かかる
講演のあと少しだけ時間があったので、ブルーバックスの『小惑星探査機「はやぶさ」の超技術』に川口教授のサイン貰いました。